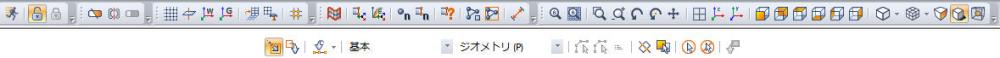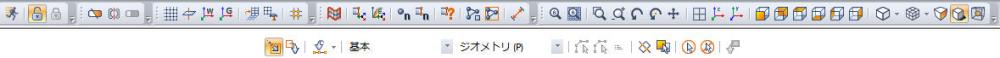|

弾性境界要素作成方法
1. 地盤の入力物性の中から弾性係数を使ってKv0を算定します。(算定式は次の通りです。)
 
ここで、E0 : 地盤の弾性係数、 a : 実験条件による係数 (上表参考)
|
次の試験方法によるひずみ係数E0 (kfg/cm2)
|
a
|
|
常時
|
地震時
|
|
直径30cm の剛体円板による平板載荷試験の反復曲線で求めたひずみ係数の1/2
|
1
|
2
|
|
ボーリング孔内で測定したひずみ係数
|
4
|
8
|
|
供試体の一軸または三軸圧縮試験で求めたひずみ係数
|
4
|
8
|
|
標準貫入試験のN 値でE0=28Nで推定したひずみ係数
|
1
|
2
|
2. 1. 算定されたKv0を使って地盤反力係数Kv(= Kh)を再計算します。
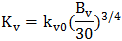
ここで、 
この際に面積Avは地盤反力バネが設置される区域の面積となります。
下図の様なモデルがあった場合
Ground Aの面積Av=1m(モデル左側の長さ)*1m(2D解析時の単位幅)=1m2、Bvは1m=100cmとなります。
同じ方法でGround Bの有効幅Bv=√(20000)cm=141.42136 cmとなります。
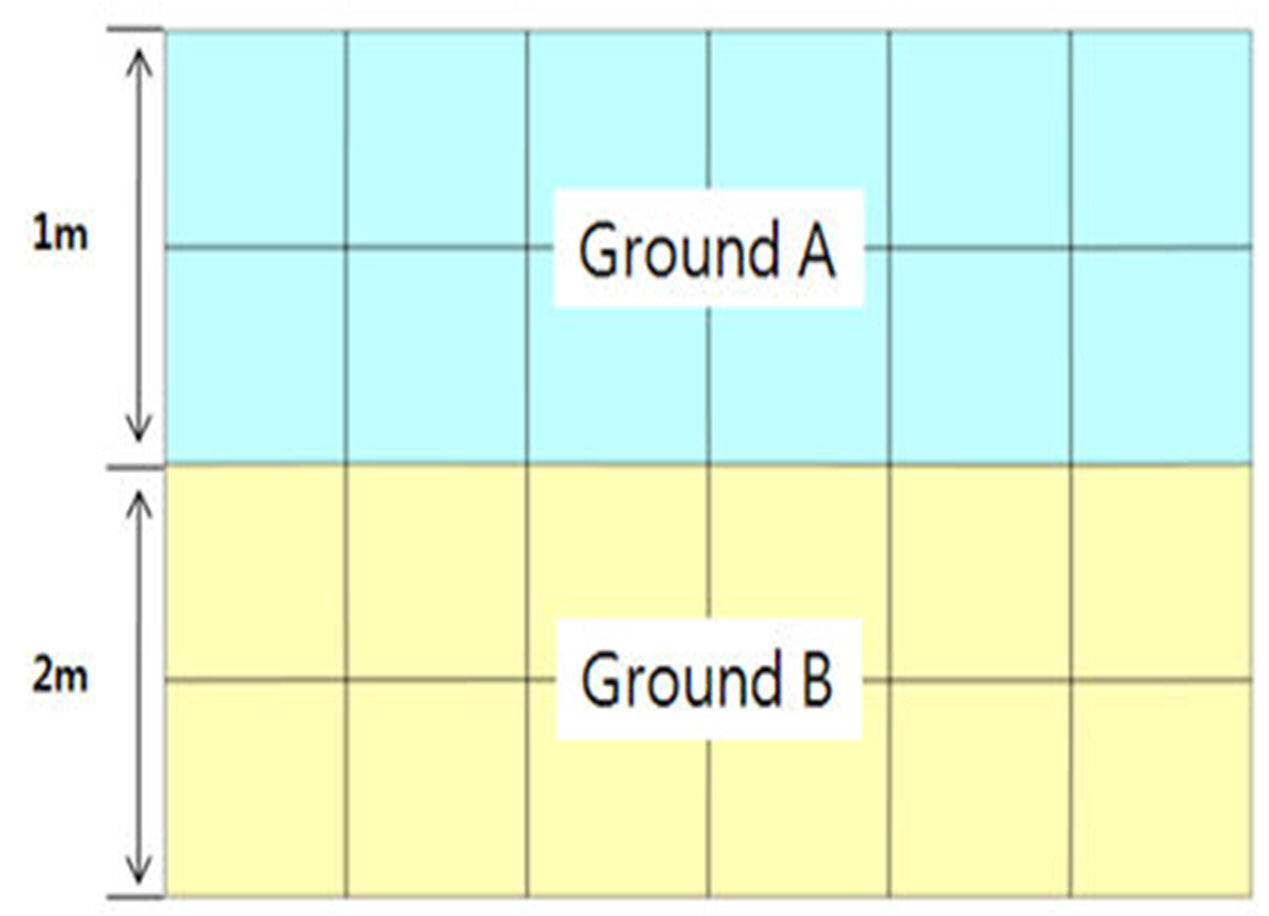
最終的に下のように地盤反力係数K値を算定して要素の面積が考慮された1節点バネが節点に作成されます。
|
|
E (tonf/m2)
|
Ky0
|
A (cm)
|
B
|
K (tonf/m3)
|
α
|
|
Ground A
|
1000
|
3.3333
|
1.00E + 04
|
100
|
1351.186643
|
1
|
|
Ground B
|
2000
|
6.6667
|
2.00E + 04
|
1414213562
|
2083.845925
|
1
|
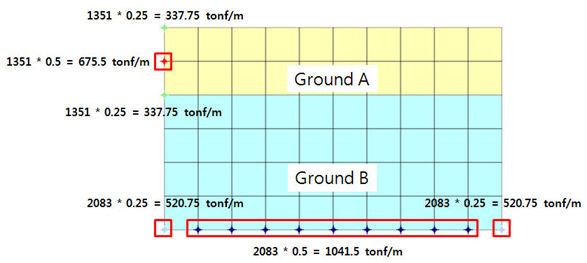
底面部 (Z方向)のバネ係数はX方向と同じ値で作成されます。
(要素の長さx幅(1m)=断面積なので要素の有効長のみを考慮します。)
地盤と地盤が合う部分では重複された2つの境界要素が作成されます。
粘性境界要素作成方法
1. Cp、 Csの算定
Cp、 Csは以下の式で計算されます。
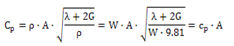
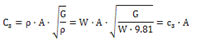
ここで, , ,  , ,
λ : 体積弾性係数、 G : せん断弾性係数、 E : 弾性係数、 ν : ポアソン比、 A : 断面積
2. 断面積の場合、surface springが作成される際に自動的に考慮されるのでCp、 Csのみを算定します。
| |
弾性係数
|
体積弾性係数
|
せん断弾性係数
|
単位重量
|
ポアソン比
|
P波
|
S波
|
| |
E
(tonf/m2)
|
λ
(tonf/m2)
|
G
(tonf/m2)
|
W
(tonf/m3)
|
ν
|
Cp
(tonf·sec/m3)
|
Cp
(tonf·sec/m3)
|
|
GroundA
|
1000
|
864.1975309
|
370.3703704
|
1.8
|
0.35
|
17.1605
|
8.2437
|
|
GroundB
|
2000
|
1459.531181
|
751.8796992
|
2
|
0.33
|
24.5792
|
12.381
|
tonf·sec/m3 単位のCp、 Csに断面積が掛けられて最終的な粘性境界要素のバネ剛性はtonf·sec/mとなります。
陰影で表示されたセルのparameterはユーザーがモデル化の際に入力する地盤の物性であり、体積弾性係数とせん断弾性係数は弾性係数+ポアソン比を使って計算します。したがってユーザーが粘性境界要素を作成する場合、追加的に入力する事項はありません。
粘性境界要素を自動的に作成する場合、以下のように要素の面積(有効長*単位幅)を考慮して自動的にバネが作成されます。バネが作成される節点に垂直な方向の係数にCpを入力して平行な方向にCsの値が入力されます。
例えば、モデルの左/右側に作成されるバネ係数のCxは各地盤のCp値であり、CzはCs値になります。
底面部はバネ係数のCzがCp値になります。
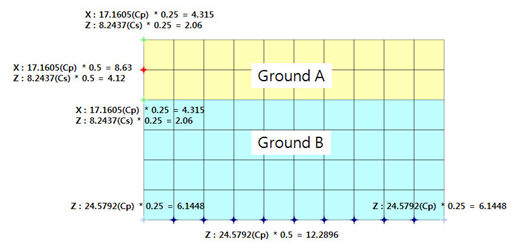

|