ファイバー要素の材料の定義
ファイバー用を用いた非弾性時刻歴解析を行うために鉄筋とコンクリートの応力-ひずみ関係を定義します。
各モデルは提案者の示方規定によって異なります。
リボンメニュー : モデル > 材料 & 断面 > 非線形特性 > ファイバー要素の材料
ツリーメニュー : メニュータブ > モデリング > 材料&断面 > ファイバー要素の材料
 ファイバー要素の材料の定義
ファイバー要素の材料の定義
梁要素の断面を小さなファイバーに分割して各ファイバーセルが特定の応力-ひずみ関係を持つようにします。
ファイバー材料に対する特性を定義します。
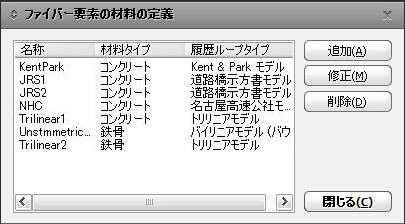
 名称
名称
ファイバー要素の名前
 材料タイプ
材料タイプ
履歴モデルを定義する材料を選択します
 履歴ループタイプ
履歴ループタイプ
履歴モデルを定義する材料を選択します。
■ コンクリート
 Kent
& Park モデル
Kent
& Park モデル
Modified Kent & Park Concrete モデルで、横拘束効果(Confinement Effect)等を考慮できます。
f'c : コンクリート圧縮強度
K : 拘束効果による圧縮強度の増加効果を表現する係数
ε_cu : 圧縮Crushing発生時のひずみ
ε_c0 : 最大圧縮強度発現時のひずみ
Z : 圧縮降伏以後、コンクリートの軟化区間の剛性を表すための係数
 コンクリート標準示方書モデル
コンクリート標準示方書モデル
日本コンクリート標準示方書[耐震性能調査編, p23]のモデルで最大応力点を超えた軟化領域と残留塑性変形、
除荷再載荷時の剛性低下効果を反映しています。
fc' : コンクリートの最大圧縮強度
ε'_peak : 最大圧縮強度発現時のひずみ
 道路橋示方書モデル
道路橋示方書モデル
日本道路橋示方書同解説、V耐震設計編[鉄筋拘束コンクリート、p.161]のモデルです。
地震 タイプ I : 極限ひずみと最大圧縮強度時のひずみが同じになって下降勾配(Edes)区間を持っていません。
地震タイプ II : 極限ひずみは示方規定式によって算定され、下降勾配(Edes)区間を持ちます。
Ec : コンクリートのヤング係数
σ_ck : コンクリートの設計基準強度
σ_sy : 横拘束鉄筋の降伏点
α, β : 断面補正係数
Note
円形断面の場合にはα=1.0, β=1.0
梯形断面、中空円形断面及び中空梯形断面ではα=0.2, β=0.4
A_h : 横拘束鉄筋1本当たりの断面積
s : 横拘束の間隔
d : 横拘束の拘束長で、帯筋や中間帯筋によって分割拘束された内部コンクリートの辺の中で一番長い辺の長さにする。
σ_bt : コンクリートの引張強度
σ_cc : 横拘束鉄筋で拘束されたコンクリートの強度
 名古屋高速公社モデル
名古屋高速公社モデル
名古屋高速公社(名高社)のモデルとして、[コンクリートを部分的に充填した剛性橋脚の耐震性能調査(案) p.7]のモデルです。
σ_ck : コンクリートの圧縮強度
ε_cc : コンクリートの圧縮強度到達時のひずみ
K : 圧縮強度増加を反映するための係数
ε_cu : コンクリートの極限圧縮ひずみ
ε_t0 : コンクリートの最大引張強度発現しのひずみ
ε_t1 : コンクリート引張破壊発生時のひずみ
ε_tu : コンクリートの極限引張ひずみ
 Trilinear Concrete
Model
Trilinear Concrete
Model
引張部と圧縮部両方を定義できるモデルであり、圧縮部はトリリニア履歴を持ちます。トリリニア履歴を定義するための
応力-ひずみで入力する方式と応力-剛性低減率で入力する方式の2つの方式があります。
σ_c1 : コンクリートの1次圧縮降伏強度
σ_c2 : コンクリートの2次圧縮降伏強度
σ_c3 : コンクリートの2次圧縮降伏以後の強度(K3算定時に必要)
ε : コンクリートの最大引張強度発現時のひずみ
ε_t1 : コンクリート引張破壊発生時のひずみ
ε_tu : コンクリートの極限引張ひずみ
ε_c1 : コンクリートの1次圧縮降伏ひずみ
ε_c2 : コンクリートの2次圧縮降伏ひずみ
ε_c3 : コンクリートの2次圧縮降伏以後のひずみ(K3算定時に必要)
ε_cu : コンクリートの3次圧縮降伏ひずみ
K1 : コンクリートの初期剛性
K2/K1 : コンクリートの1次降伏後の剛性と初期剛性の比
K3/K1 : コンクリートの2次降伏後の剛性と初期剛性の比
ε_cu : コンクリートの3次圧縮降伏ひずみ
Note
'σ - ε'入力方式で、ε_c1~ε_c3を入力した状態で、'σ - α'入力方式を選択すると自動で
剛性K1, K2/K1, K3/K1を計算してくれます。その逆も自動で計算されます。
■ Steel
 Menegotto-Pintoモデル
Menegotto-Pintoモデル
Menegotto and PintoのSteelモデルをFilippouなどが修正したモデルです。
f_y : 鉄筋の降伏強度
E : 鉄筋の初期剛性
b : 降伏後、鉄筋の剛性と初期剛性の比
R0, a1, a2 : 降伏後、鉄筋の応力-ひずみ曲線挙動状態を定義する常数
 バイリニアモデル
バイリニアモデル
一般的な対称バイリニア(Bilinear)鉄筋モデルです。
f_y : 鉄筋の降伏強度
E1 : 鉄筋の初期剛性
E2/E1: 降伏後の鉄筋の剛性と初期剛性の比
![]() Uバイリニアモデル(バウシンガー効果考慮)
Uバイリニアモデル(バウシンガー効果考慮)
一般的なバイリニア型鉄筋モデルを発展させたモデルとして、降伏後の鉄筋の剛性を任意で定義できるし、
鉄筋の座屈と破断などを考慮できます。
σ_y : 引張側圧縮強度
σ_cy : 圧縮側圧縮強度
ε1 : 鉄筋の圧縮座屈発生時のひずみ
ε2 : 引張降伏後の鉄筋破断発生時のひずみ
E1 : 鉄筋の初期剛性
E2 : 引張降伏後の鉄筋の剛性
E3 : 載荷時に鉄筋の降伏以後の剛性
E4 : 圧縮降伏以後の鉄筋の剛性(?-?値を指定すると負勾配を考慮することができます。)
E5 : 圧縮降伏が発生した鉄筋の座屈以後の剛性
 Trilinear Steel Model
Trilinear Steel Model
3つの勾配を持つトリリニアモデルとして、履歴入力を応力-ひずみの座標で入力する方式と剛性の低減率で
入力する方式の2つがあります。
σ1y : 引張側1次降伏強度
σ2y : 引張側2次降伏強度
σ3y : 引張側2次降伏後強度(K3算定時に必要)
σ'1y : 圧縮側1次降伏強度
σ'2y : 圧縮側2次降伏強度
σ'3y : 圧縮側2次降伏後強度(K5算定時に必要)
ε1y : 引張側1次降伏ひずみ
ε2y : 引張側2次降伏ひずみ
ε3y : 引張側2次降伏後ひずみ(K3算定時に必要)
ε'1y : 圧縮側1次降伏ひずみ
ε'2y : 圧縮側2次降伏ひずみ
ε'3y : 圧縮側2次降伏後ひずみ(K5算定時に必要)
K : 鉄筋の初期剛性
K2/K1 : 1次引張降伏後の鉄筋の剛性と初期剛性の比
K3/K1 : 2次引張降伏後の鉄筋の剛性と初期剛性の比
K4/K1 : 1次圧縮降伏後の鉄筋の剛性と初期剛性の比
K5/K1 : 2次圧縮降伏後の鉄筋の剛性と初期剛性の比
Note
'σ - ε'入力方式で、ε1y~ε'3yを入力した状態で、'σ - α'入力方式に変換すると自動でそのひずみに該当する
剛性K1, K2/K1, K3/K1を計算してくれます。その逆も自動で計算されます。