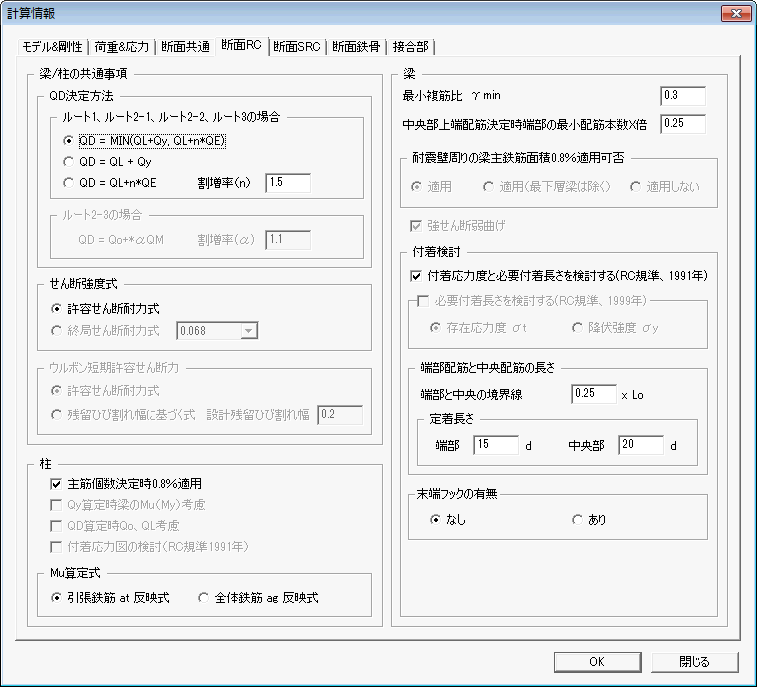計算情報 - 断面RC
断面算定と保有水平耐力算定に必要な断面RC関連オプションを設定します。
リボンメニュー : 2次設計 > 計算情報 > 断面RC
ツリーメニュー : 2次設計タブ > 計算情報 > 断面RC
計算情報-断面RCのダイアログボックス
 梁/柱共通事項
梁/柱共通事項
QD決定事項
ルート1、ルート2-1、ルート2-2、ルート3の場合
ルート1、ルート2-1、ルート2-2、ルート3の場合はオプションの選択が可能です。
(1) QD = MIN(Qo + Qy, QL+n*QE) : (2)と(3)の中で小さい値を適用します。
(2) QD = QL + Qy (Qy = ΣMy/l')
(3) QD = QL + n*QE、nは割増率です。
Note1
(2)の判定ではQoではなくてQLを使用しています。
QD = Qo + Qy 部分を Q1 = QL + a1*SUM(Mu)/Lを使用しており、 a1=1.0, SUM(Mu)/L=Qy で使用しています。
せん断強度式
計算ルートが2-3の場合、短期許容せん断力式を指定します。
許容せん断耐力式 : せん断ひび割れ強度に基づく計算式
 柱
柱
主筋個数決定時0.8%適用
チェックオンすると、断面選定時に主筋全断面積(ag)が0.8%DBを満足する主筋個数を求めます。
付着応力図の検討(RC規準1991年)
1991年度版 RC規準17条を参考にして、付着の検討を行います。
Mu算定式
Qy計算時の柱Mu(My)の計算方法を選択します。
引張鉄筋at反映式 : at よる 2007年版 技術基準解説書(付1.3-10~12)式
全体鉄筋ag反映式 : agよる 2007年版 技術基準解説書(付1.3-13~15)式
 梁
梁
(1/4 位置の断面算定をデフォルトで行っています。)
最小複筋比γmin
主筋本数を選定する際の最小複筋比γを指定します。
設計用曲げモーメントが下端部が引張になる場合は最小値を「0.3」、軽量コンクリートの場合は「0.4」とします。
中央部上端配筋本数決定時端部の最小筋配本数X倍
中央部上端の主筋本数はγの最小値と関わらず端部上端主筋本数のX倍を最小必要本数とします。
付着検討
付着応力度と必要付着長さ検討(RC規準1991年)
チェックすると必要付着長さを検討します。
端部配筋と中央配筋の長さ
端部と中央の境界線
端部配筋と中央配筋の境界を柱面間距離(L0) に対する比で指定します。
定着長さ
端部と中央部の定着長さを主筋径の倍率で指定します。
末端フックの有無
末端フックの有無を指定します。