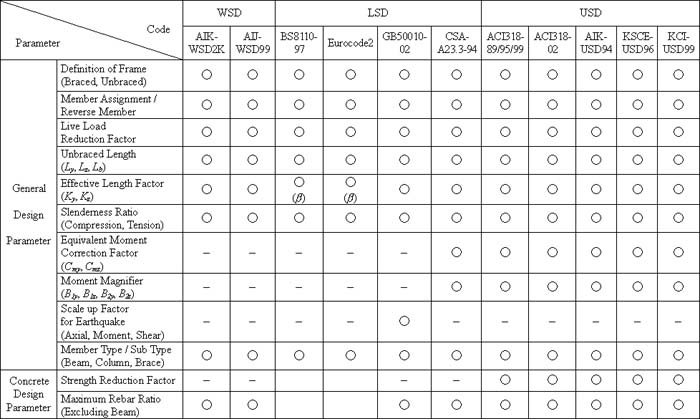コンクリート設計規準
鉄筋コンクリート部材の断面設計または部材検定実行時に適用する設計規準と、耐震設計のための特別規定を
適用するかどうかの設定を行います。
リボンメニュー : 設計 > 設計パラメータ > RC > 設計規準
ツリーメニュー : メニュー タブ > 設計 > RC設計パラメータ > 設計規準
次のようなダイアログで入力します。
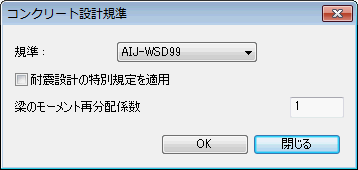
コンクリート設計規準ダイアログボックス
 規準
規準
鉄筋コンクリート設計規準[デフォルト = AIJ-WSD99](Note 1 を参照)
 耐震設計の特別規定を適用
耐震設計の特別規定を適用
耐震設計に対する特別規定の適用の可否を選択
![]() モーメント再分配係数
モーメント再分配係数
梁部材に適用されるモーメント再分配係数を入力します。ここで入力する係数は全体梁部材に一括的に適用します。
Note
この機能はモデル全体の梁部材に一括適用されます。特定の梁部材にのみモーメント再分配係数を適用する場合は 設計 > RC設計パラメータ > モーメント再分配率を利用します。
Note 1
適用可能な鉄筋コンクリート部材の設計規準は次の通りです。(*はオプション設計規準です)
- 日本建築学会の鉄筋コンクリート構造計算規準(AIJ-WSD99)
- アメリカのコンクリート学会の鉄筋コンクリート構造計算規準(ACI318-19)*
- アメリカのコンクリート学会の鉄筋コンクリート構造計算規準(ACI318M-19)*
- アメリカのコンクリート学会の鉄筋コンクリート構造計算規準(ACI318-14)*
- アメリカのコンクリート学会の鉄筋コンクリート構造計算規準(ACI318M-14)*
- アメリカのコンクリート学会の鉄筋コンクリート構造計算規準(ACI318-11)*
- アメリカのコンクリート学会の鉄筋コンクリート構造計算規準(ACI318-08)*
- アメリカのコンクリート学会の鉄筋コンクリート構造計算規準(ACI318-05)*
- アメリカのコンクリート学会の鉄筋コンクリート構造計算規準(ACI318-02)
- アメリカのコンクリート学会の鉄筋コンクリート構造計算規準(ACI318-99)
- アメリカのコンクリート学会の鉄筋コンクリート構造計算規準(ACI318-95)*
- アメリカのコンクリート学会の鉄筋コンクリート構造計算規準(ACI318-89)*
- イギリスのコンクリート構造設計基準(BS8110-97)
- ヨーロッパのコンクリート構造設計基準(Eurocode 2:04)*
- ヨーロッパのコンクリート構造設計基準(Eurocode 2)
- コロンビアの耐震建築規準-終局強度設計(NSR-10)*
- カナダの鉄筋コンクリート構造計算規準(CSA-A23. 3-94)
- 中国の国家標準鉄筋コンクリート構造計算規準(GB50010-10)
- 中国の国家標準鉄筋コンクリート構造計算規準(GB50010-02)
- 大韓コンクリート学会の建築物コンクリート構造設計基準(KDS 41 30:2018)*
- 大韓コンクリート学会のコンクリート構造設計規準(KCI-USD12)*
- 大韓コンクリート学会のコンクリート構造設計規準(KCI-USD07)*
- 大韓コンクリート学会のコンクリート構造設計規準(KCI-USD03)*
- 大韓コンクリート学会のコンクリート構造設計規準(KCI-USD99)
- 大韓土木学会のコンクリート標準示方書(KSCE-USD96)
- 大韓建築学会の鉄筋コンクリート構造計算規準(AIK-USD94)
- 大韓建築学会の鉄筋コンクリート構造計算基準(AIK-WSD2K)
- インドの国家標準鉄筋コンクリート構造計算規準 (IS456:2000)*
- 台湾の鉄筋コンクリート構造計算規準(TWN-USD100)*
- 台湾の鉄筋コンクリート構造計算規準(TWN-USD92)*
- フィリピン構造基準(NSCP 2015)*
Note 2
鉄筋コンクリート部材設計時の入力変数の設計規準別の使用可否は次の通りです。